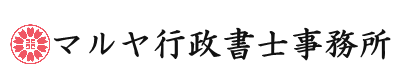1,特殊車両とは
自動車を運転するかたはお分かりだと思いますが、道路では実に多種多様な自動車が往来しています。自動車の高さ・幅・長さ・重さも様々です。
また道路も片道が複数車線の広い道路もあれば、対向車と離合することも困難で、どちらか一方が待機しなければ離合できない狭い道路もあります。軽自動車・乗用車は一方通行、進入禁止道路を除き、特に通行に関する制限はありませんが、一定のサイズ(高さ・幅・長さ・重さ)を超える自動車は、道路を走行する権利が認められていません。禁止されている行為を解除することを「許可」と言いますが、一定のサイズを超える車両のことを特殊車両と言い、運行するためには「特殊車両通行許可」をあらかじめ、道路管理者から取得することが必要になります。また、無許可で道路を運転することは違法行為となります。
私自身、約10年間路線バスの運転士をしておりましたが、そのうち約5年間は姫路市内を中心に乗務をしていました。特に旧姫路市内は、世界遺産である姫路城を中心に広がる城下町です。道路が狭いうえ、一方通行道路が多数あります。日々の乗務のなかで、土地勘のない観光バスが狭小道路を逆走して来ると言った事例に幾度となく遭遇しました。
「特殊車両通行許可制度」は、このようなことを未然に防ぐため、一定のサイズ(高さ・長さ・重さ)を超える自動車は、あらかじめ自走経路を申請し、行政庁が走行可能と判断した道路に限り、走行することができる制度と言えます。
特殊車両通行許可申請では、主に
➀特殊車両に該当する車両
②特殊車両が通行できる道路
③違反したときの罰則規定
が定められています。「➀特殊車両に該当する車両」は建設用車両・農業用車両も該当しますので、私有地でなく、公道を走行する場合は許可の取得が義務付けられています。
それでは最初に「➀特殊車両に該当する車両」ものを見ていきます。
1-2,道路法に基づく車両の制限
| 車両の諸元 | 一般的制限値 | |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5m | |
| 長さ | 12。0m | |
| 高さ |
高さ指定道路:4.1m |
|
| 重さ | 総重量 |
高速自動車国道、重さ指定道路:軸重の長さに応じて最大25トン |
| 軸重 | 10トン以下 | |
| 隣接軸重 |
18トン:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 |
|
| 輪荷重 | 5トン | |
| 最小回転半径 | 12。0m | |
さらに、セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。(車両制限令第3条第2項)
1-3,総重量の特例(車両の通行の許可の手続きを定める省令第1条の2)
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、または自動車の運搬用に限ります。
| 道路種別 | 最遠軸距 | 総重量の制限値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高速自動車国道 | 8m以上 9m未満25トン | 25トン |
首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路 |
| 9m以上 10m未満26トン | 26トン | ||
| 10m以上 11m未満27トン | 27トン | ||
| 11m以上 12m未満29トン | 29トン | ||
| 12m以上 13m未満30トン | 30トン | ||
| 13m以上 14m未満32トン | 32トン | ||
| 14m以上 15m未満33トン | 33トン | ||
| 15m以上 15.5m未満35トン | 35トン | ||
| 15.5m以上36トン | 36トン | ||
| 重さ指定道路 | 8m以上 9m未満 | 25トン | |
| 9m以上 10m未満 | 26トン | ||
| 10m以上 | 27トン | ||
| その他の道路 | 8m以上 9m未満 | 24トン | |
| 9m以上 10m未満 | 25.5トン | ||
| 10m以上 | 27トン |
1-4,長さの特例セミトレーラ・フルトレーラ
車両制限令第3条3項
| 道路種別 | 連結車 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高速自動車国道 | セミトレーラ連結車 | 16.5メートル | |
| フルトレーラ連結車 | 18.0メートル |
1-5,特殊車両通行許可の違反車両に対する罰則規定
| 違反内容 | 違反条項 | 措置内容 |
|---|---|---|
| 無許可 | 法47条第2項 |
積載貨物が分割可能な場合は「軽減措置」 |
| 無許可(車両諸元違反) | 法47条第2項 | |
| 無許可(経路違反) | 法47条第2項 | |
| 許可証不携帯 | 法47条の2第6項 |
電話等により通行条件を確認できない場合は、 |
| 通行条件違反 | 法47条の2第1項 |
通行時間違反は「夜間通行」(時間まで通行中止) |